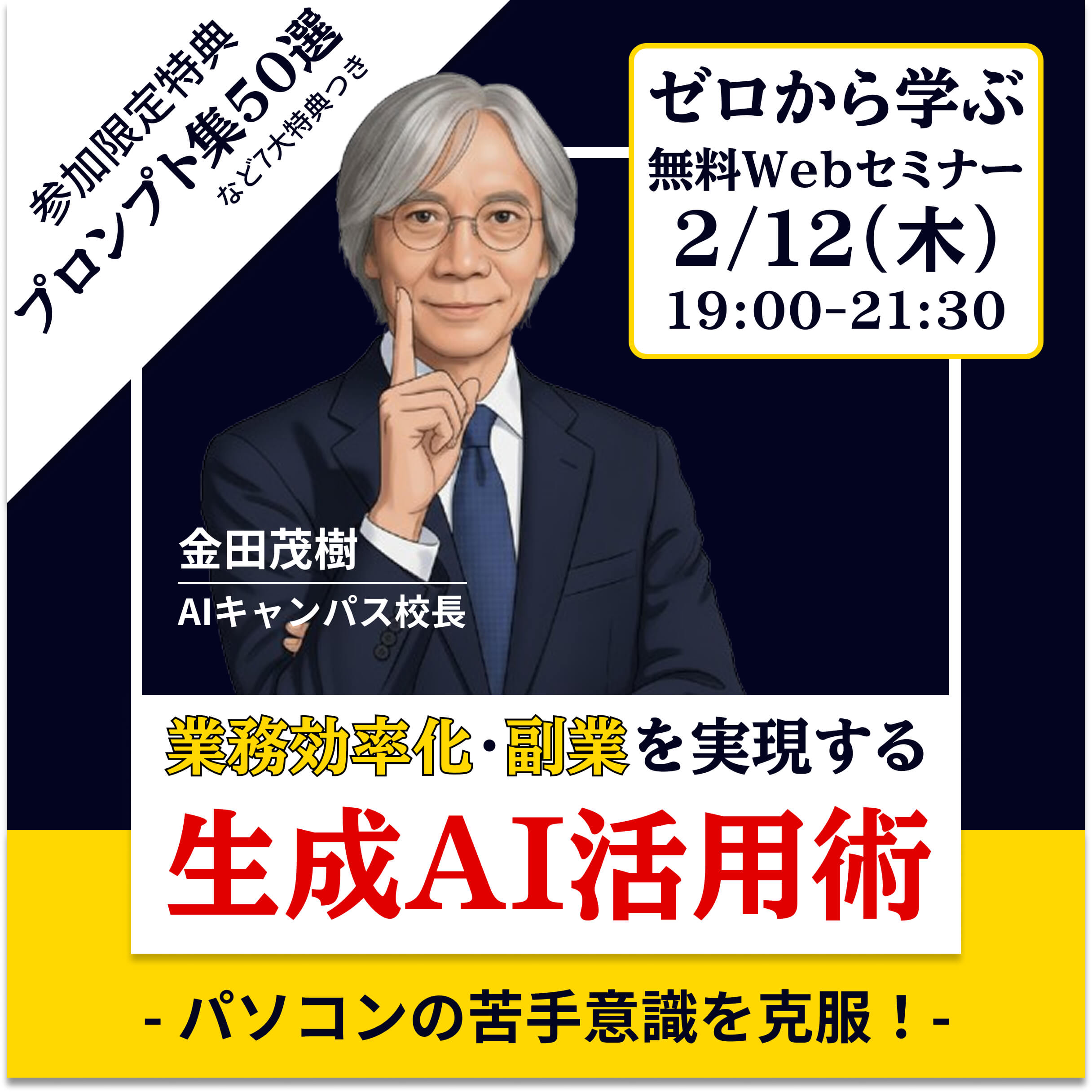difyとは?主な5つの機能、利用すべき理由、活用例などを解説
Difyとは?
どんなことができるの?
利用する際の注意点は?
AIを活用したいけれど、どこから始めていいかわからない人も多いのではないでしょうか。
そんなときに注目されているのが、ノーコードでAIアプリを作れる「Dify(ディファイ)」です。プログラミング知識がなくても、AIチャットボットや文章生成ツールを自分で作れるのが魅力です。
GPTやClaudeなど複数のモデルを組み合わせて使えるため、用途に合わせた柔軟な設計ができます。
この記事では、Difyについて以下の内容を解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
Dify(ディファイ)とは?
Dify(ディファイ)とは、プログラミングの知識がなくてもAIアプリを作れるオープンソースのプラットフォームです。
Difyを使えば、チャットボットや文章生成ツールなどをノーコード・ローコードで構築でき、AIの処理部分に集中できます。具体的には、GPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)をAPI経由で扱い、それを視覚的なインターフェースで組み立てられます。
さらに、RAG機能を通じて、自社データを検索して応答に活かすことも可能です。加えて、Difyはエージェント機能や運用監視機能も備えていて、単なるプロトタイプだけでなく実運用にも対応できます。
Difyの主な5つの機能

Difyの主な機能は次の5つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
AIの流れを見える化する「ビジュアル設計」
Difyのビジュアル設計機能では、AIの処理をブロックやノードで表現し、それらを線でつなぐことで処理の流れを直感的に組み立てられます。
これにより、「ユーザー入力→モデル呼び出し→出力結果」といった一連の流れの視覚的な把握が可能です。コードを書かずに操作できるため、AIの処理構造を初心者でも理解しやすくなります。
ノードの編集や接続をリアルタイムで確認でき、処理順序や分岐のロジックをすぐに見直せます。さらに、条件分岐やAPI呼び出しなどのノードも組み込めるため、実用的なアプリ設計も可能です。
Difyの公式機能説明にも「業界をリードするビジュアルワークフロー」などの記述があります。
自社データを賢く活かすRAG機能
RAG(Retrieval-AugmentedGeneration)機能は、AIモデルに外部知識を組み込むしくみです。
Difyでは、ユーザーの質問に対してまず自社文書やデータベースから関連情報を検索し、それをモデルに渡して応答を生成します。これにより、AIが最新情報や社内情報を参照でき、誤情報やhallucinationのリスクの低減が可能です。
DifyのRAG機能はハイブリッド検索や再評価(rerank)を用いた手法もサポートし、応答の精度を高めています。最近のアップデートでは、検索アルゴリズムの改善により、質問応答の効率性が約20%向上したという報告もあります。
AIが自律的に動く「エージェント機能」
Difyのエージェント機能を使えば、AIが指示なしに判断しながら動く仕組みを作れます。
この仕組みでは、モデルに「やるべきこと」「使えるツール」「動作範囲」などを指示し、それに従ってAIが処理を分解して実行します。
DifyはFunctionCallingやReActといった推論モードをサポートし、複数ステップのタスクを自然な流れで処理が可能です。さらに、検索・計算・外部API呼び出しなどのツールをエージェントに持たせると、より実用性の高い応答が可能になります。
公式ドキュメントでは、Difyには50を超えるビルトインツールがあり、これらをエージェントに組み込めると説明されています。
プロンプト設計を効率化するIDEツール
Difyにはプロンプト設計を助けるIDEツールが備わっており、初心者でも扱いやすくなっています。
具体的には、プロンプトの文言を視覚化して比較したり、変数や文脈を調整しながらリアルタイムで反応を確認できる機能があります。
開発者向けには「ExpertMode」も用意されており、より高度なプロンプト制御やログ表示が可能です。また、GitHubの説明では、プロンプトの作成やモデルパフォーマンス比較などを直感的に扱えるインターフェースがあることが示されています。
このようなツールのおかげで、試行錯誤しながら最適なプロンプトを手早く見つけられます。
GPT・Claudeなどを自由に切り替えて最適化
DifyはさまざまなLLM(例:GPT、Claude等)を統合でき、用途に応じて切り替えて使えます。
この機能により、ある処理はGPTを使い、別の処理はClaudeを使って最適化を図る構成も可能です。
Difyのドキュメントによれば、カスタムモデルを「プラグイン」形式で追加できるため、独自モデルの導入も可能です。また、Difyは複数モデルを並行実行して応答を比較できるデバッグ機能も提供しており、最適なモデルを選ぶ判断がしやすくなっています。
このように複数モデルを使い分ける自由度が、Difyの大きな強みとなっています。
Difyを利用すべき3つの理由

Difyを利用すべき理由は主に次の3つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
コードが書けなくてもAIアプリを作れるため
Difyはプログラミング知識がなくてもAIアプリを構築できる環境を提供します。
ブロックをドラッグ&ドロップして処理フローを組み立てる形式を採用しており、コードを書く手間を省きます。画面上で各処理のつながりを視覚的に確認できるため、仕組みを理解しやすいでしょう。
また、プロンプトやモデル設定もGUIで設定可能で、初心者でも迷いにくい設計です。
こうした仕組みにより、アイデアをより早く形にしやすくなります。Difyの公式機能説明書には「視覚的なプロンプトオーケストレーション」などが記載されています。
複数のAIモデルを自由に使い分けできるため
DifyはGPT、Claude、その他オープンソースモデルなど複数のLLMを統合して使える機能を提供しています。
そのため、用途や応答特性に応じて最適なモデル選択が可能です。さらに、モデル切り替えや並列比較を簡単に試せるインターフェースも備わっており、どのモデルが最適かを見つけやすくなっています。
Difyの公式ドキュメントでは「モデル設定がカスタマイズ可能」や「マルチモデル対応」が強調されています。この柔軟性により、精度とコストのバランスをユーザーが自ら調整できる点が強みです。
試作から本格運用までスピーディに進められるため
Difyはプロトタイピング(試作段階)から本番運用までスムーズに移行できる設計です。
視覚的ワークフロー、運用監視、ログ記録といった機能が最初から備わっており、それらを段階的に有効化できます。つまり、小さく始めて徐々に拡張するアプローチが楽になるのです。
公開時は「RunApp」「サイト埋め込み」「API参照」などから配布形式を選べるため、用途に応じて展開方法を切り替えられます。デバッグでは各ノードの履歴や変数を追跡でき、運用フェーズではログを見ながら精度改善を継続できます。
こうした仕組みにより、導入後も安定した運用に移りやすいです。
Difyを利用する際の注意点3選

Difyを利用する際の注意点は主に次の3つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
高度な処理や特殊要件には限界がある
Difyは汎用的なAIアプリ構築に強みがありますが、複雑な機械学習モデルや高度な数値計算、リアルタイム推論には向かない場合があります。標準機能だけでは、細かい最適化や特殊アルゴリズムを組み込むのが難しいことがあります。
例えば、非常に大きなデータセットを扱って機械学習モデルを学習させたい場合、Dify内でそのまま処理することは困難です。
公式ドキュメントや外部レビューでも、複雑な処理タスクには制約があるという指摘があります。また、GitHub上では、長いシステムプロンプトが保存できないバグ報告もあり、プロンプト長制限などの技術的制約も確認されています。
APIコスト・制限に注意する
Difyを運用する際には、API利用量や回数の制限、コスト設計に注意が必要です。無料プランには月間利用量やリクエスト数が上限設定されており、有料プランでも高負荷時には追加費用が発生する可能性があります。
例えば、Difyの料金表では無料プランでのメッセージクレジット数やAPIレートリミットが明示されており、一定を超えると制限がかかるのです。
GitHubのIssueには、API利用量に応じたコストアラート機能の要望も見られ、現在は管理が難しい面もあるといえます。そのため、初期設計段階からAPI利用見込みを見積もり、予算枠を決めて運用することが望ましいです。
セキュリティ・データ管理体制を構築する
Difyをビジネス用途で使う場合、機密データや個人情報を扱うことがあります。その際には、APIキーの管理やアクセス制御、暗号化などのセキュリティ体制を整備しましょう。
Difyのドキュメントでは、APIキーはクライアント側に直接書き込んではいけず、サーバー側経由で扱うべきと明記されています。
また、アクセス権限を制限する機能も備わっており、必要に応じてAPI呼び出しを無効化できる設定も可能です。さらに、セルフホスト運用を選択する場合には、ネットワーク防御、認証方式、ログ保存、ソフトウェア更新などを適切に設計しなければなりません。
これらの対策を怠ると、予期せぬ情報漏えいリスクが生じます。
Difyのおすすめ活用例3選

Difyのおすすめ活用例は次の3つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
FAQ・カスタマーサポートチャットボット
Difyを使えば、企業のよくある質問(FAQ)をもとに自動応答チャットボットを短時間で作成できます。
たとえば、商品説明や返品手続き、営業時間などの質問への対応を、AIがリアルタイムで受け持つようにできます。
Difyのナレッジ登録機能で自社マニュアルやFAQをアップロードして、それを検索・参照させる設定が可能です。実際、Difyの公式ドキュメントには「数分でビジネスデータを基にしたAIチャットボットを作成できる」と説明があります。
このように顧客対応を自動化すれば、対応負荷の軽減とユーザー満足度の向上が期待できます。
ナレッジ検索・社内文書応答アシスタント
社内文書やマニュアルを検索して、質問に答えるアシスタントをDifyで構築できます。
まず、社内のドキュメントやPDF、テキストファイルをナレッジベースとして登録して、その内容をAIに参照させます。Difyの検索+応答機能により、ユーザーが「この仕様の詳細は?」と尋ねると、関連文書を自動で引き出して回答が可能です。
Difyのガイドでは、検索・全文取得・再評価(rerank)を使ったハイブリッド検索をサポートしていると紹介されています。
これにより、業務効率化や情報共有がスムーズになり、社員が必要な知識をすぐに得られるようになります。
コンテンツ生成・文章支援ツール
Difyを使って、記事・SNS投稿・商品説明などを自動生成するツールを構築できます。
たとえば、ブログタイトル案出し、文章の骨子作成、キャッチコピー作成などをAIに任せることが可能です。
実際には、プロンプトを設定し、テーマや語調、文字数などを変数として渡す構成を作ります。このような自動化は、コンテンツ制作の効率を大幅に上げ、クリエイティブな作業に注力できるようになる利点があります。
例えば、配信先ごとにトーンやCTA、文字数を自動調整する運用も容易です。
さらにテンプレートを再利用でき、品質とスピードを両立できます。
Difyについてよくある質問
Difyについてよくある質問は次の3つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
プログラミング経験なしでも使える?
Difyはコードを書かずにAIアプリを構築できる設計になっており、プログラミング経験がない方でも利用しやすいです。
ブロックやノードをつなぐ直感的な操作でワークフローを作成でき、専門知識がなくても動く仕組みを設計できます。
実際、Difyの公式機能説明にはビジュアルオーケストレーションを強調した記述があり、初心者向け設計を意識していることが窺えます。また、設定時もモデルプロバイダーの追加やAPIキー設定などをGUIベースで行え、複雑な設定画面を扱う必要がほとんどありません。
このような設計により、技術バックグラウンドがない人でもアイデアを形にするハードルを大幅に下げられます。
どのLLMモデルが使える?
DifyはOpenAI(GPTシリーズ)やAnthropic(Claude)をはじめ、多くの商用・オープンソースモデルをサポートしています。
モデルプロバイダーの一覧によれば、AzureOpenAI、Gemini、GoogleCloud、Nvidiaなども利用可能です。各モデルのパラメータや特性は異なるため、用途やコストに応じて選べます。
Difyのブログでも、OpenAIo1モデルを設定し利用する手順が紹介されており、簡単にモデル切り替えができることが示されています。
無料プラン・有料プランの違いは?
Difyはクラウド版でSandbox(無料)プランを提供しており、最初は200回分のメッセージクレジットが無料で付与されます。
有料プランにはProfessional($59 /月)やTeam($159 /月)などがあり、メッセージ数の上限、ドキュメント数、ストレージ容量、API利用制限の緩和などで差があります。無料プランではログ保持期間が短かったり、API利用率に制限がかかったりするため、大規模な用途や商用運用を目指すなら有料プランが現実的です。
また、Difyは教育用途向けに特別なプランを提供しており、学生や教員にはProfessionalプランが無償で提供されることもあります。
まとめ
この記事では、Difyについて以下の内容を解説しました。
Difyは、AIの力を身近にし、誰でもアイデアをすぐ形にできるツールです。
ノーコードで設計できる使いやすさと、GPTやClaudeなどの高性能モデルを自由に選べる柔軟さが、多くのユーザーに支持されています。試作から本格運用まで一貫して進められるため、企業だけでなく個人クリエイターにも活用価値があります。
もし「AIを使って自分のサービスを作ってみたい」と感じたなら、まずは無料プランから試してみるのがおすすめです。
Difyを活用すれば、あなたのアイデアが現実のアプリとして動き出すかもしれません。