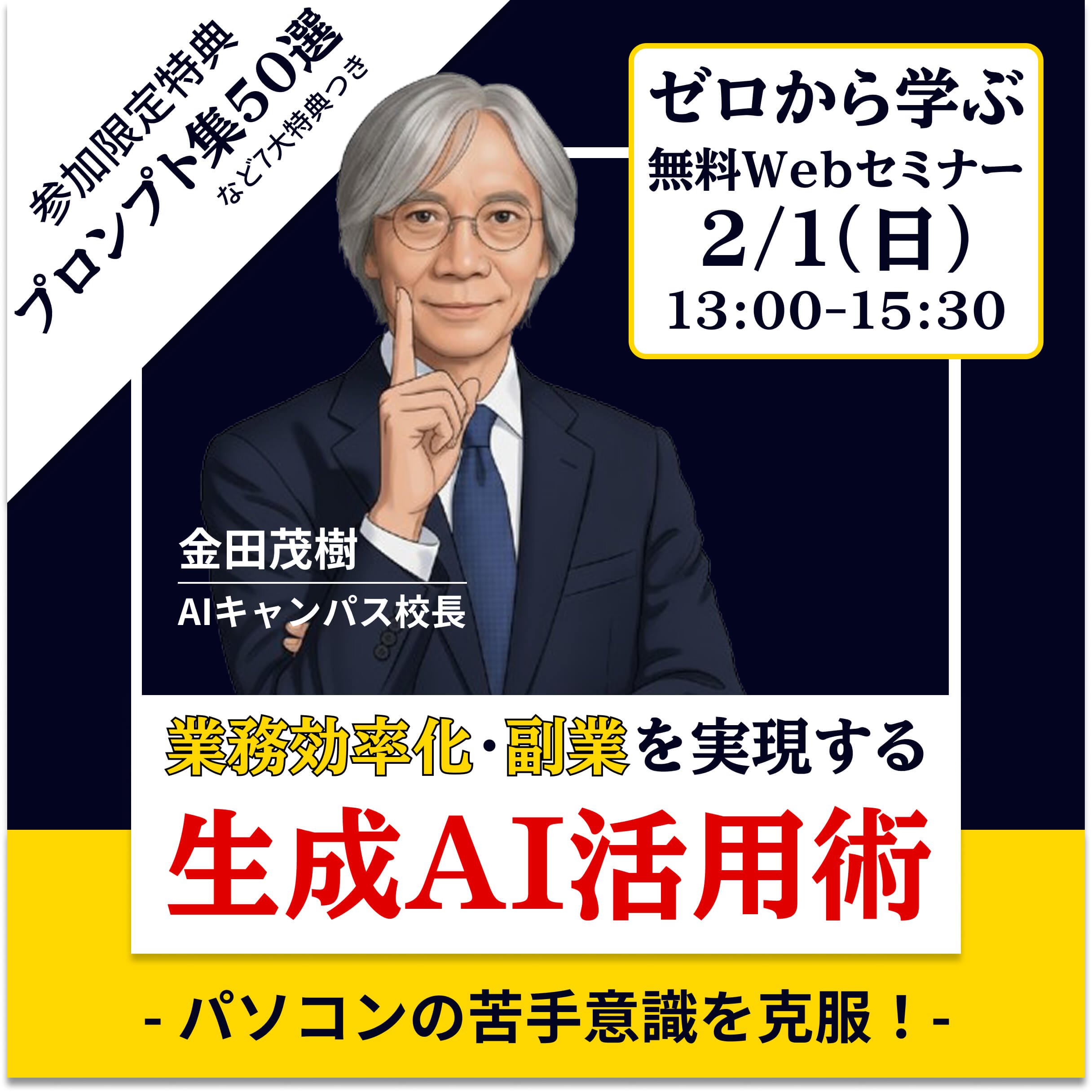5分でわかる!生成AIとAIの違い【初心者向けにわかりやすく解説】
生成AIとAIは何が違うんだろう?
用途にも違いがあるのかな…
ChatGPTやGeminiといったツールの登場を機に、話題や注目を集めている生成AI。見聞きする機会が増え、関心が増している人は多いのではないでしょうか。
ただ、気になるのはこれまで聞いてきた「AI」との違い。直感的に別物だというイメージはあるものの「生成」という言葉がつくか否かで実際にどのような違いがあるのか、あいまいな人もいるはず。
そこで本記事では次のトピック別に、生成AIとAIの違いを解説します。
「生成AIやAIは使うべきなのか」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、生成AIとAIの違いが明確になりますよ。
- AIは適切な答えを選ぶ仕組みがある
- 生成AIは新しい答えを作り出せる違いがある
- 生成AIの活用は専門知識が不要である
『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』
そんな方へ、
- 生成AIに作業や仕事を任せる方法
- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ
- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク
を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!
パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。
参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。
本記事を音声で聴く
【意味・仕組み】生成AIとAIの違い
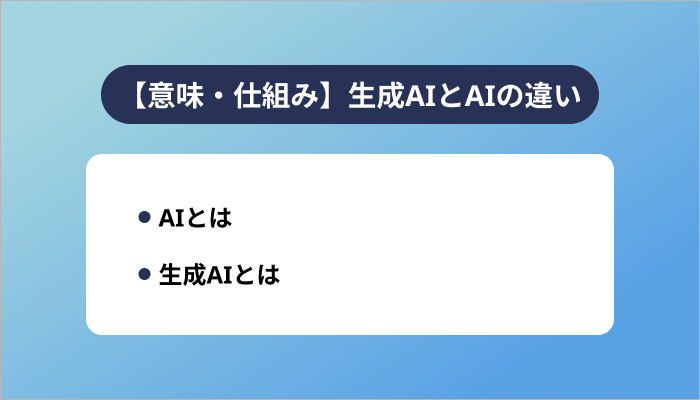
| 意味 | |
|---|---|
| 生成AI | 文章や画像など、指示内容に応じて新しいコンテンツを生み出すAI |
| AI | 判断や予測など、人間の思考を模した処理を行う技術の総称 |
生成AIとAIはどちらも人工知能の一種ですが、生成AIは新しい答えをつくり出す技術、AIは正しい答えを見つける技術という違いがあります。なお、人工知能とは人間のように考えたり判断したりする力をコンピュータに持たせる技術のことです。
ここからはそれぞれの特徴を掘り下げて解説します。
AIとは

AIは、正解のある問いに対して最適な答えを導くという点で違いがあります。
入力されたデータを数値化し、過去の情報と比較することで、正解パターンに当てはまるかを判断します。例えば犬の画像を読み込ませると色や輪郭などの特徴を数値として捉え、過去に学習したデータと照合し「これは犬だ」と認識するなどです。
AIの中心となる技術が機械学習です。大量のデータから傾向や規則を見つけ、分類や予測に活かす手法です。さらに複雑な処理ができる深層学習(ディープラーニング)という技術もあります。
いずれも大量のデータの中から判断の手がかりを見つけ出し、状況に応じた適切な答えを探すための技術です。AIの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

生成AIとは

生成AIは、新しいコンテンツを自動で生み出すという点で違いがあります。
従来のAIが正解に近いものを選ぶ分類や予測を目的としていたのに対し、生成AIは目的や文脈に応じて新しい出力をつくり出す点で大きく異なります。
例えば文章生成AIのChatGPTでは「この文章の続きを自然に書くにはどんな言葉が続くか?」を高速で判断し、文を生成する仕組みです。
こうした仕組みには文章に用いられる大規模言語モデル(LLM)や、画像生成に使われる拡散モデルなど、用途ごとに異なる技術が使われています。上記モデルを総称して生成AIと呼びます。
生成AIの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

【できること・用途】生成AIとAIの違い
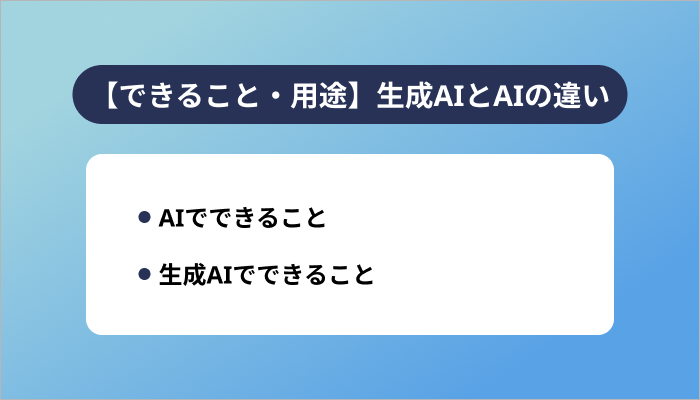
| できること | |
|---|---|
| 生成AI | ・文章生成 ・画像/動画生成 ・音楽生成 など |
| AI | ・画像認証 ・レコメンド ・需要予測 ・内容の整理/分類 など |
生成AIは正解のない問いに対して新たな成果物を生み出すことができ、AIは正解のある問いに対して最適な答えを導くことが可能です。
ここからは生成AI・AIでできることをそれぞれ掘り下げて解説します。
AIでできること

従来型のAIは、正解のある問いに対して最適な答えを選ぶ処理ができるという点で違いがあります。こうした特性から次のようなことが実行できます。
| AIでできること | 具体例 |
|---|---|
| 画像認証 | iPhoneの顔認証(Face ID)など |
| レコメンド | Amazon、Netflixのおすすめ機能など |
| 需要予測 | 在庫管理や、飲食店の売上・来客数予測など |
| 内容の整理/分類 | Gmailの迷惑メール自動振り分けなど |
上記はすべて過去の事例にもとづいて、適切な答えを導く技術の応用となります。
ただしあくまでも過去のデータから、正解や正解に近いパターンを導き出すのが中心です。新たなアイデアや示唆を自発的に生み出すことはできません。
AIのできること・できないことをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
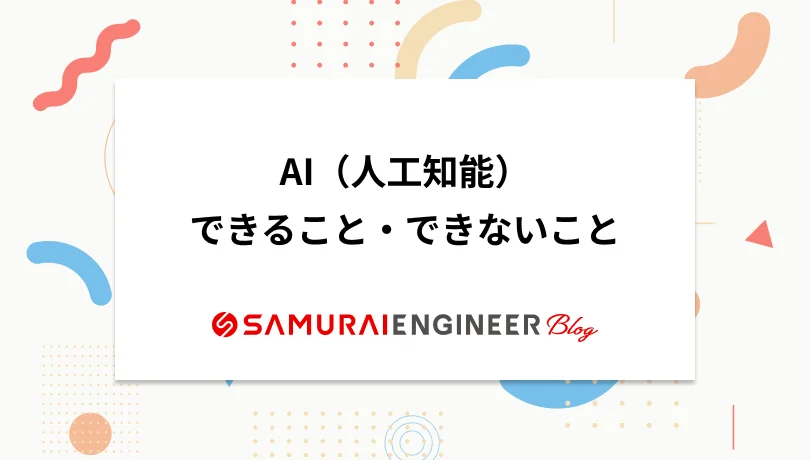
生成AIでできること

生成AIは、正解のない問いに応じた成果物を生成できるという違いがあります。プログラミング言語ではなく日本語で指示できるよう設計されているため、技術に詳しくない人でも扱いやすくもなっています。
| 生成AIでできること | 具体例 |
|---|---|
| 文章作成 | メール文作成や議事録、報告書作成、翻訳文作成など |
| 画像・イラスト生成 | SNS投稿用イラスト素材作成、バナー画像作成など |
| 音声生成 | ナレーション音声の作成、音声広告の作成など |
| 動画生成 | PR動画の構成案作成、字幕の自動生成など |
| プログラミング | コードの作成、エラー箇所の修正など |
人に頼むような感覚で業務を依頼できる点が、従来のAIとは異なる点です。
とはいえ人の感情を理解することはできず、仮に道徳的に問題のある内容でも合理的で効率的だと判断すれば生成されてしまいます。そうした判断の切り分けはまだ得意ではありません。
生成AIのできることをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
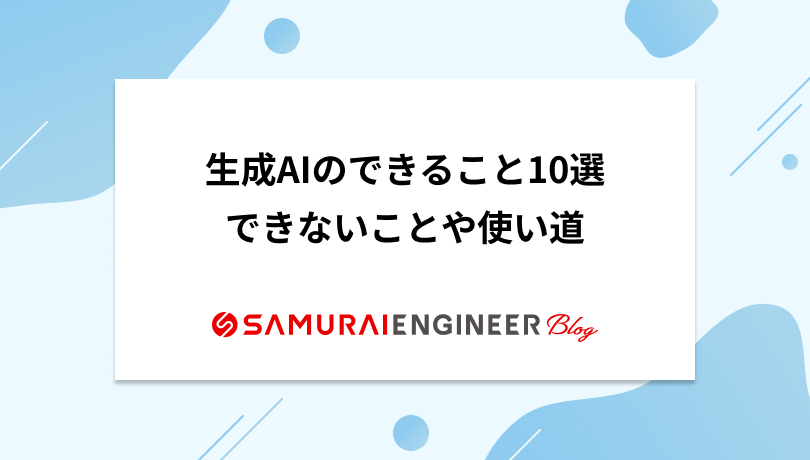
【活用に必要な知識】生成AIとAIの違い

| 活用に必要な知識 | |
|---|---|
| 生成AI | ・目的を定める力 ・プロンプト(指示文)のスキル |
| AI | ・Pythonなどのプログラミング言語知識 ・データクレンジングや前処理など、データ分析のスキル ・機械学習の基礎知識 |
生成AIは特別な知識がなくても扱え、AIは専門的な知識やスキルが必要な違いがあります。以降ではそれぞれの活用に必要な知識を掘り下げて解説します。
AI活用に必要な知識

AIの活用には、次のような専門知識が必要です。
- Pythonなどのプログラミング言語の知識
- データクレンジングや前処理など、データ分析のスキル
- 機械学習の基礎知識
AIは大量のデータを前提とする仕組みのため、こうした土台が必要です。
例えば需要予測や画像識別のシステムでは、もともと用意された機能をそのまま使うような場合なら、容易に導入できるでしょう。しかし、社内の判断基準に合わせたり出力内容を変更したりするためには専門知識が必要です。
あらかじめ用意された機能をそのまま使うだけなら比較的扱いやすいものの、目的に応じて変更する場合は、それ相応の知識と準備が必要となります。
生成AI活用に必要な知識

生成AIの活用には「目的を定める力」と「プロンプト(指示文)を組み立てる力」が必要です。
プログラミングやデータ分析のような専門知識は不要ですが、何を出力させたいのかを明確にし、その条件や要素を具体的に指示する力が求められます。
例えば文章を生成する場合「何について・誰向けに・どんなトーンで書くか」といった点を整理し、それが伝わる形で指示に落とし込まなければ、意図とずれた成果物になる可能性があります。
生成AIは与えられた情報をもとに結果を組み立てる仕組みのため、曖昧な目的や不足した指示では精度が下がります。生成AIを使いこなすには専門技術というよりもむしろ「何を求めるか」を考え「どう伝えるか」に工夫を加える力が必要なのです。
必要な知識を踏まえた上で、生成AIの活用を始めるまでの手順を知りたい人は次の記事を参考にしてください。
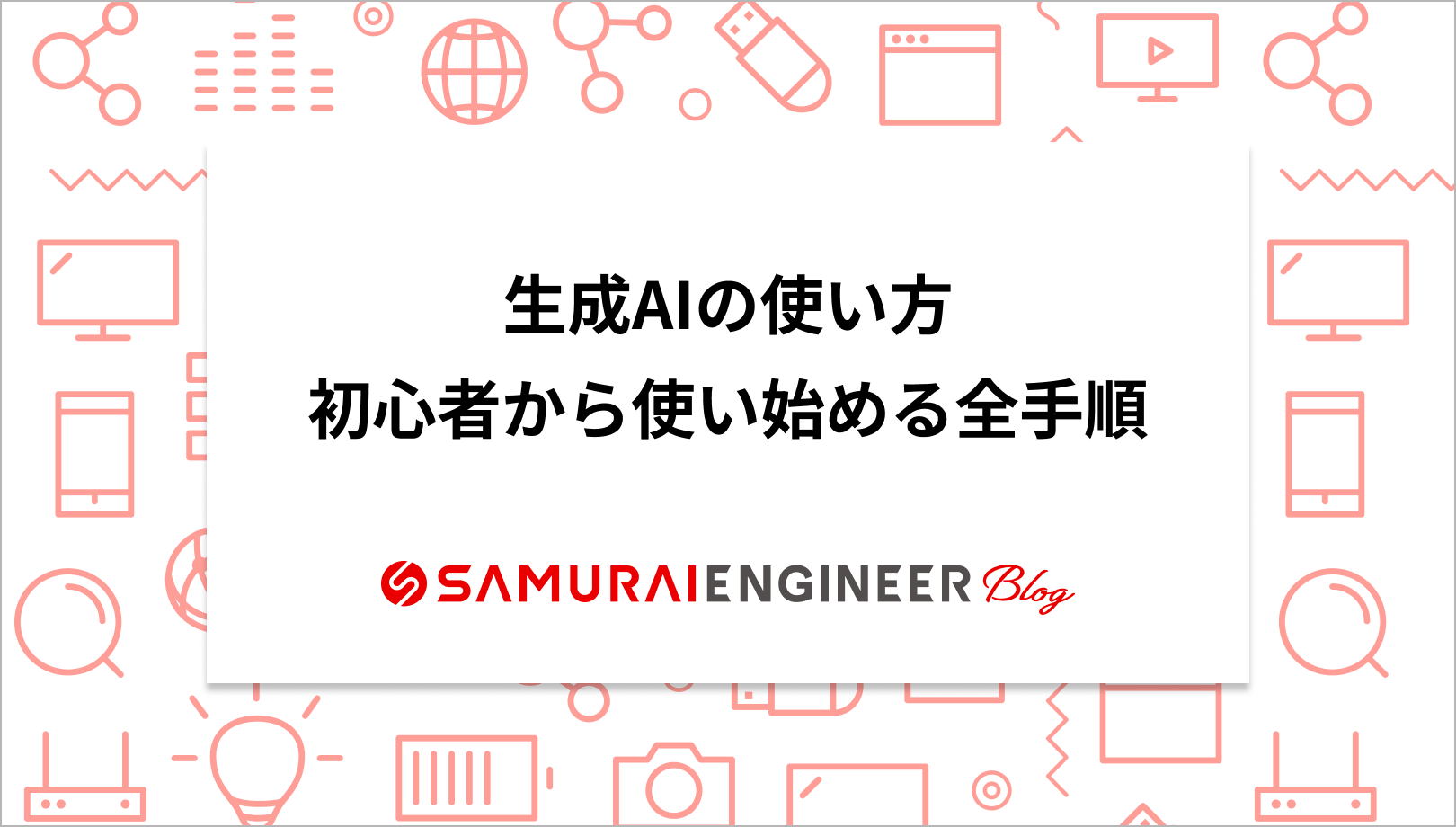
AI・生成AIは使うべき?
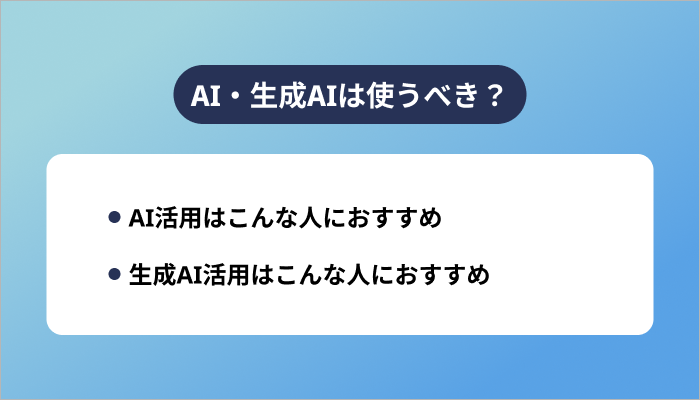
| こんな人におすすめ | |
|---|---|
| 生成AI | ・考えがあるのにうまく表現できない人 ・効率的に成果物を作成したい人 |
| AI | ・選択に迷うことが多い人 ・根拠を持って行動したい人 |
基本的に、AIも生成AIも積極的に使うべきです。ただし自分の目的や状況に応じて、どちらをどう使うかを見極めることが重要です。
ここからは生成AI・AIそれぞれをどんな人が使うべきか、掘り下げて解説します。
AI活用はこんな人におすすめ

AIの活用は、次のような人におすすめです。
- 選択に迷いやすく、判断に根拠を持ちたい人
- 感覚や経験ではなく、データに基づいた意思決定をしたい人
- 正攻法やセオリーに沿って、業務を効率化したい人
AIは過去の実績や行動パターンをもとに、状況に応じた判断の手がかりを提示するのが得意です。そのため直感や勘だけに頼らず、根拠に基づいて行動したい人にとって非常に有効です。
例えば商品の発注量を決める場面で「どれくらい仕入れるべきか」と悩むことがあるとします。その際AIを活用すれば、過去の販売実績や季節要因などをもとに在庫の過不足を予測し、判断の根拠となる情報を得ることが可能です。感覚や勘に頼らず、計画的な仕入れが可能となります。
業務効率化はもちろん、選択に根拠を求める人や正攻法を知りたい人にAIの活用をおすすめします。AIの活用例について、詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

生成AI活用はこんな人におすすめ

生成AIは、次のような人におすすめです。
- 考えがあるのに、うまく言葉や形で表現できない人
- 作業にかかる時間や負担を減らしたい人
- 手早くたたき台やアイデアを出したい人
生成AIが効率的な成果物づくりをサポートしてくれます。
例えば文章や画像・動画の作成では、言い回しや構成に迷って手が止まることがあります。そんなとき生成AIにたたき台を出してもらえば作業の見通しが立ちやすくなり、制作の負担を軽減することが可能です。
ほかにも商品の紹介文を考える場面で、性能や特徴を理解していても「どう伝えればよいか」と悩むことがあります。生成AIを使えば方向性を確認しながら内容を整理できるため、迷いを減らす助けになります。
伝え方に迷う人や作業の負担を減らしたい人にとって、生成AIは頼れるサポート役となるためおすすめです。生成AIの活用事例について、詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。
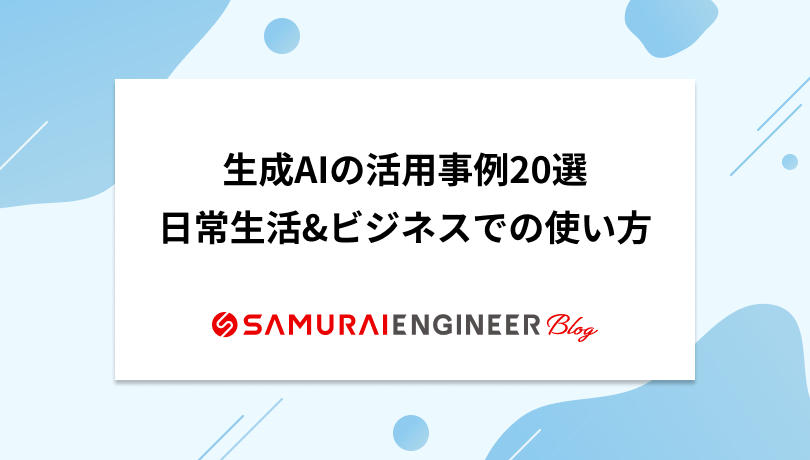
まとめ
本記事では生成AIとAIの違いについて整理しました。
従来のAIは過去のデータをもとに正解を導く仕組みで、分類や予測が得意です。一方で生成AIは正解が定まらない問いにも対応し、新たな文章や画像を生み出すことができます。
扱ううえで必要な知識にも差があり、生成AIは専門的なスキルがなくても使える点が特徴です。両者の違いを正しく理解し、目的や用途に応じた使い分けに役立ててください。
内容を踏まえ、理解を深めるきっかけとなれば幸いです。